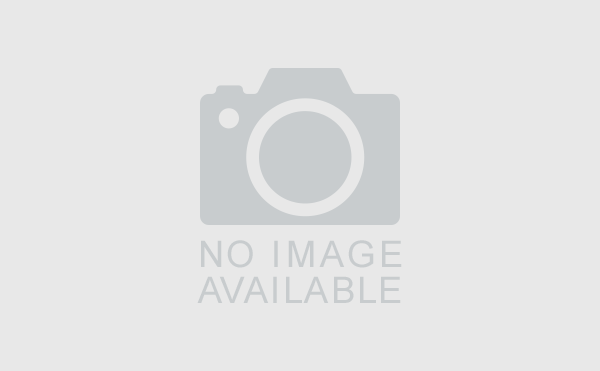子持トンネル(山形県小国町)の銘板を見て。
山形県西置賜郡小国町より、小ネタを1つ。
山形県の南西部に位置する小国町(おぐにまち)。その小国町には小学校が2校しかない。1校は小国町中心部に位置する「小国小学校」であり、小国町のほとんどの地域がこの小国小の学区となる。そしてもう1校が「叶水小学校」(「叶水」は「かのみず」と読む)で、叶水小学校の学区は、大字で言うと「叶水」「新股」「河原角」「大石沢」「市野々」の5つだけである(「小国町例規集」内の「小国町立小学校・中学校通学区域に関する規則」より)。この記事では、この大字5つをまとめて「叶水地区」と呼ぶことにしよう。なお、叶水地区は、基督教独立学園高等学校の所在地としても知られている。
この叶水地区は山々に囲まれているが、外側と自動車で行き来できる主要ルートが5本もある(林道を含めるともう数本ある)。まずは地図をご覧いただこう。地理院地図とGoogleマップ、どちらもそれぞれに長所と短所があるので、今回はどちらも表示しておくことにする。
5つのルートを簡潔に紹介すると、
- 九才峠【南東方面】(県道8号;飯豊町中津川地区方面)※冬期閉鎖
- 極楽峠【西方面】(県道15号;小国町足水中里・市野沢方面)※冬期閉鎖
- 子持トンネル【北西方面】(県道8号;小国町中心部方面)
- 横川ダム沿いの道路【北方面】(小国町道;小国町綱木箱口方面)
- 桜峠【北東方面】(県道15号;小国町白子沢・沼沢方面)※冬期閉鎖
である(県道は地理院地図で黄色で表示)。
さて、先日(令和4年4月3日)、このルートのうちの一つ「子持トンネル」を通って叶水地区を訪れた。ちなみに5本のうち3本はまだ冬期閉鎖中であった。

4月になったというのに、トンネルの周りはまだ雪で覆われていた。トンネルの外観はこれといって変わったところはなく、強いて言えば少し簡素かな、といったところ。トンネルの前には「頭上落雪注意」「スリップ注意」という看板があり、どちらにも「山形県」と書いてある。

ここは県道8号であり、県が看板を設置するのは当然のことだ。しかしながら、トンネルを通りながら銘板を確認してみると、ちょっと驚いたことがあった。

銘板には「山形県」ではなく、「北陸地方建設局」の文字があったのである。「地方建設局」というのは旧建設省の地方支分部局であり、2001年の中央省庁再編後は国土交通省の「地方整備局」にあたる組織である。ここでおもしろい点は2点。
- 山形県道であるのに国土交通省が建設していること。
- 山形県なのに「北陸」地方建設局が建設していること。
都道府県道や市町村道なのに国土交通省が建設している道路施設といえば、ダム関連の付替道路ということが多い。この叶水地区の北側にも先述の通り「横川ダム」がある。このダムは1987年着工、2008年竣工というダムで、建設省・国土交通省の直轄のダムである。この子持トンネルのルートはダム建設に伴う付替道路というにはちょっとダムからは離れているように思えるのだが、時期もちょうど一致しており、ダム建設によって立ち退きを余儀なくされた住民などもいて、地元住民への見返りの意味もあったのかなと思った。
次に、地方整備局の管轄区域を見てみると、山形県は全域が東北地方整備局の管轄であり、実際に小国町を横断する国道113号(指定区間である)沿いの看板や銘板を見ると「東北地方建設局」「東北地方整備局」の文字がある。しかし、小国町に降った雨水は山形県を代表する河川「最上川」には流れず、新潟県の荒川へと流れていく。河川行政は水系ごとに行うため、荒川水系はその河口(新潟県村上市)を管轄している北陸地方整備局が(山形県部分も)行っているのである。それで子持トンネルは山形県では珍しい「北陸地方建設局」が建設したトンネルになってしまったのである。
帰宅後に家にあった1999年発行の地図(昭文社「県別マップル」)を見てみたところ、子持峠には車道が通じておらず、点線の表記であった。では県道8号はどこを通っていたかというと、北方面へ横川沿いに綱木箱口に抜ける道路が県道8号だったのである。この道路もダムに沈んでしまうこととなったため、ダム建設に伴って付け替えられ、現在は町道になっている(先程のリストで「横川ダム沿いの道路【北方面】(小国町道;小国町綱木箱口方面)」と書いた道路)。つまり、北陸地方建設局・北陸地方整備局は、叶水地区の住民のために、ダムになる横川沿いの県道を付け替えるのみならず、子持峠を経由する小国町中心部への短絡路(子持トンネル)を建設し、ダム沿いの道を県道ではなく町道とし、子持トンネルのルートを県道にした、ということになる。
このようにダム沿い(河川沿い)のルートを残しながら、ダム沿い以外のルートも補償のために建設するというのはけっこうあることなのだろうか。
ちなみに、このあと叶水地区からの帰りにはダム沿いの町道を通って帰った。町道に接続する県道15号の「叶水トンネル」でも、ダム沿いの町道の「境の峰トンネル」でも、銘板には「北陸地方整備局」の文字があった。こちらのルートのほうが新しいようだったので、工事中にこのルートが使えなくなる期間(旧県道8号がダム工事で通行止めになってから、この新しい町道が完成するまでの期間)が何年間かあり、その際に叶水地区の住民が困らないように子持峠経由のルートを建設したのかなとも思った。




ここに載せている写真にある情報とダムの建設年や建設省・国交省の管轄に関することは調べて分かったことだが、その先はあくまで推測でしかない。もし推測に間違いがあることを知っている人がいれば教えてほしい。きっと建設史みたいなものもあるんだろうが、それを調べるほどの元気はない。
中央省庁再編があったおかげ(?)で、「子持トンネル」は「山形県唯一の「北陸地方建設局」と書いてある銘板がついたトンネル」であるような気がするのだがどうなのだろうか。ほかにもあったらぜひ教えてほしい。
追記。横川ダムの建設についての来歴と子持峠について参考になりそうなリンクがあったので、紹介しておく。
★「新・県民ケンちゃん~子持峠」
子持峠の旧道に関するブログ記事だが、この峠の来歴に付いての記述も詳しい。
★「横川ダムのあゆみ – 横川ダムと白い森おぐに湖」
国土交通省北陸地方整備局羽越河川国道事務所による公式サイトより、横川ダム建設に関わる年表のページ。ここでは県道8号が「主要地方道川西小国線」と、県道15号が「主要地方道玉川沼沢線」と、ダム沿いの町道が「町道横川ダム湖岸線」と、それぞれ表記されている。これによると、子持トンネルルートの開通は2001年11月、ダム沿いのルートの開通は2004年11月だったようである。