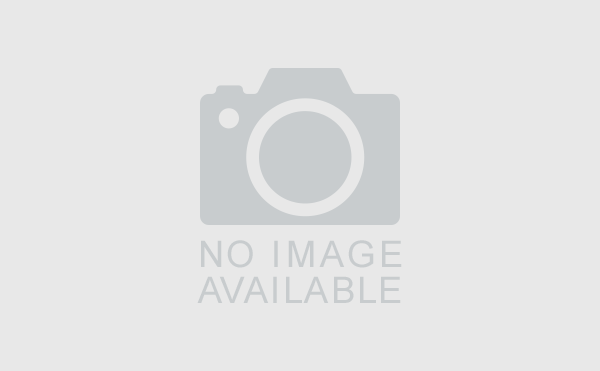「民法-条文沿革」を更新しました ~民法の改正の歴史を概説~
あけましておめでとうございます。年末年始の休みを利用して、ダウンロードコンテンツ内法令カテゴリの「民法-条文沿革」を更新しました。このファイルは、民法のひとつひとつの条(複数の項に分かれている条については、項ごと)が明治29年の制定以来どのように改正されてきたかをまとめたものです。
<ダウンロードはこちらから>
これまで公開していたものは平成28年6月現在の内容で作成したもので、今回は令和3年10月現在の内容に更新したので、約5年分の改正を書き加えたことになります。この5年間で、民法では重要な改正が相次いで行われました。本ファイルのページ数も、128ページから155ページにまで大幅に増加しました。
民法は、5つの大きな「編」から成り立っています。内容をかいつまんで説明すると、以下のようになります。
- 第1編 総則
- 民法全体に関する規定。
- 未成年、後見・保佐・補助、錯誤や詐欺などの場合の意思表示、代理、権利の時効など
- 第2編 物権
- 人がものに持っている権利について。
- 所有権、占有、抵当権など
- 第3編 債権
- 人が人に対して持っている権利について。
- 契約や損害賠償請求など
- 第4編 親族
- 親族関係のでき方とその効果について。
- 婚姻・親子・養子・扶養など
- 第5編 相続
- 死者の財産の分け方について。
- 相続人・相続分・遺言など
このようにかなり幅広い内容を1つの法律でカバーしており、民法と関わらないで人生を送ることはできないと思います。ものを所有せず、契約もせず、親族もおらず、という人はいないでしょうから。
さてこの民法は、法形式上は、明治29年に制定されたものを何度も一部改正しながら(その数、61回!)現在も使い続けていることになっています。しかし、一部改正とは言いながらも大改正を何度も受けていて、明治29年の内容をそのまま引き継いでいるところはほとんどなくなっています。そのあたりもこのファイルを眺めていただけるとよく分かるかと思います。
例えば、相手に何か損害を加えた人は損害賠償責任を負うという旨を規定した第709条は、制定当時は、
第七百九条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
明治29年法律第89号(制定当時)のころの条文
という条文だったのが、現在は、
(不法行為による損害賠償)
平成16年法律第147号による改正を受けた後の条文(現行の条文)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
となっています。口語化されて分かりやすくなっていることが分かるでしょう。ただ、この条では内容には大きな変化はありません。
法定利率(契約などで利率を定めなかった場合に使われる利率)を定めた404条は、内容についても大きな改正を受けています。制定当時の条文は、
第四百四条 利息ヲ生スヘキ債権ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ其利率ハ年五分トス
明治29年法律第89号(制定当時)のころの条文
というものだったのが、現在は、
(法定利率)
平成29年法律第44号による改正を受けた後の条文(現行の条文)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
という長たらしい条文になっています。内容も、法定利率は年5%だったのが、年3%となり、3年ごとに変動しうるものとなりました。
明治29年以来、どのような大改正を受けてきたかの概略を以下に示します。なお、字の色は、ファイルの中の字の色と対応しています。
- 明治29年法律第89号「民法(民法第一編第二編第三編)」
- 第1編~第3編を制定。
- 明治31年法律第9号「民法(民法第四編第五編)」
- 第4編・第5編を追加。ただし、いわゆる「家」制度に基づいた内容で、現行の内容とは大きく異なる。
- このとき、第4編・第5編の目次は第4編の直前に書かれた。
- その後、明治に2回、大正に2回、昭和元年~22年4月に4回の小さな改正
- 昭和22年法律第222号「民法の一部を改正する法律」
- 日本国憲法の規定にのっとり、男女平等・個人主義に立脚し、第4編・第5編を全面的に改正。第4編・第5編は口語化する。第1編~第3編も一部改正(文語のまま)。
- その後、昭和23年~64年に18回、平成元年~16年6月に15回の小さな改正
- 平成16年法律147号「民法の一部を改正する法律」
- 第1編~第3編を全面口語化(内容については、ほぼ改正なし)。第1編~第5編に項番号を付す。これで民法もようやく現代の法律と同じ体裁となった。
- 第4編の直前に付されていた第4編・第5編の目次は、第1編の前に付されていた第1編~第3編の目次に統合された。このことと民法全体が口語化されたこととにより、民法第1編~第5編が見た目の上でもひとつの法律にまとまった感じがした。
- その後、平成17年~28年に9回の小さな改正
- ここまでの内容で「民法-条文沿革」を作成し、公開していた。ここからは、今回のファイル更新の内容となるので、民法の改正を小さな改正まですべて記載していくこととする。
- 平成29年法律第44号「民法の一部を改正する法律」
- いわゆる「債権法大改正」。第1編・第3編を中心にかなり大規模な改正がなされた。現状に合わせるために内容を改正したり、これまで解釈や判例で補われていた部分を明文化したりしたもの。令和2年4月1日に施行された。
- 平成30年法律第59号「民法の一部を改正する法律」
- 成人年齢を20歳から18歳へ引下げ。婚姻適齢を「男18歳以上、女16歳以上」から「男女とも18歳以上」へ改正。令和4年4月1日に施行される。
- 平成30年法律第72号「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
- いわゆる「相続法改正」。遺留分制度の規定の整理、「特別の寄与」制度の創設、自筆証書遺言の方式の緩和、「配偶者居住権」の創設、などの内容。
- 令和元年法律第2号「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」
- 民法的には小さな改正。
- 令和元年法律第34号「民法等の一部を改正する法律」
- 特別養子縁組の要件について、6歳までであったのを15歳までに改正。
- 令和3年法律第24号「民法等の一部を改正する法律」
- 第2編第3章「所有権」を中心とする、相隣関係・共有・所有者不明土地などに関する改正。
- 令和3年法律第37号「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」
- 民法的には小さな改正。
- 令和3年法律第61号「国家公務員法等の一部を改正する法律」
- かつて民法を改正した法律の附則を改正しただけで、実質的な影響はなし。
ということで、前回のファイル作成時から8回の改正がありました。
この5年間の民法改正がどれほど大規模であったかは、ファイルの中の青色の字(と水色の字)の多さを見ていただければ分かるかと思います。特に、平成29年法律第44号の債権法改正があまりにも大規模で、このファイルの更新作業も途中で何度も挫折してしまい、滞ってしまっていました。令和元年末の年末年始の休みから毎年コツコツと作業を続けてきて、今回ようやく完成に至ったため公開したところです。ただ正直なところ、校閲まできちんと行えている自信はありません。もしミスを発見した際には遠慮なく教えてください。というか誰か校閲してくれないでしょうか。
この「条文沿革」シリーズは、なかなかよその無料サイトには類似のコンテンツはないと思うのですが、本当にアクセス数が少ないコンテンツです。需要がないのでしょう。個人的にはかなり興味深いので、こうして面倒な作業を行いながら作っているのですが。民法以外の条文沿革も少しずつ更新していこうと思います。